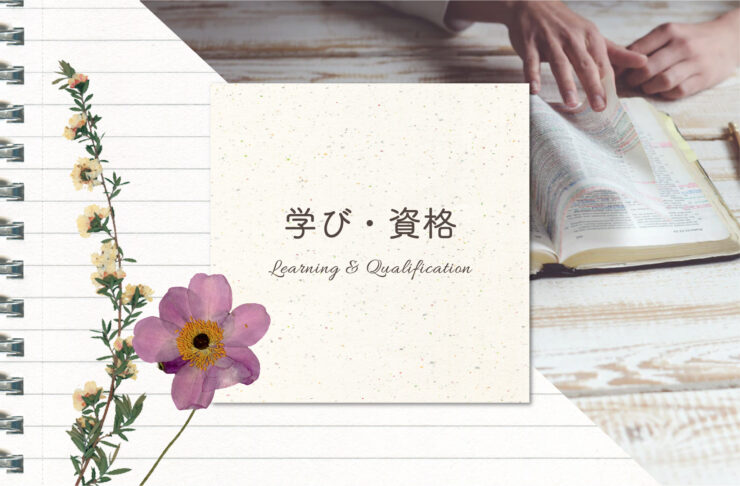
公認心理師になって、得たもの、失ったもの
昨年「公認心理師」に合格しました。
開業カウンセラーの私にとって、
「国家資格」の取得は大きなメリットだと信じていました。
しかし。
今年になり、公認心理師として実際に活動してみて、
得たものと同時に、失ったものがあると感じています。
結論を一言で言うなら、
「国家資格」のお墨付きと引き換えに、
一部の「職と自由」を失った
・・・のです。
この記事では、公認心理師となって「得たもの」「失ったもの」、
そして「私の物申したい!」、この3つを書きたいと思います。

公認心理師になって「得たもの」
公認心理師になって得たものは、大きく以下3つです。
【1】国家資格の信頼
【2】新しい知識
【3】連携の視点
得たもの【1】国家資格の信頼
まず一番大きいのは、先ほども書いたように、
「国家資格」という一定の信頼を得られる資格を取得できたことです。
カウンセラーやセラピストの資格は本当に玉石混交で、
あやしいもの、お手軽なものも、たくさんあります。
そのような中で、お客様に安心して選んでもらうために、
「国家資格」を持っているということは、
やはり一定の信頼を得られるようです。
私は、カウンセラーとしての資格は複数持っていますが、
やはり、このことは大きいと感じています。
得たもの【2】新しい知識
次に、この資格を取得するために、新しく得られた知識・情報がありました。
公認心理師は、「医療」「教育」「福祉」「司法」「産業」の5分野で活躍し、
連携が取れることを期待されています。
私は元教員で、産業カウンセラーの資格も仕事も持っていたので、
「教育」「産業」分野については、ある程度理解しているつもりでした。
そして「医療」分野については、
日々の臨床で必要に迫られる部分を、
多少は勉強している、情報取得している、
という感じでした。
ですが、「司法」と「福祉」の分野については、
正直弱かったんですよね。
それを、今回 資格取得するにあたって、
例えば高齢者福祉とか、少年犯罪に関わる法律や制度などを、
概要でしょうが、学ぶ機会を得られました。
例え、自分が直接その分野で働くことがないとしても、
クライアントさんの相談内容によっては、
それらの知識が役立つ場面があります。
受験勉強は大変だったけれど、学べて良かったと思っています。
得たもの【3】連携の視点
3つめに、公認心理師に求められている
「多職種との連携」という視点を、前より強く持てたことです。
10年以上カウンセリング業をしてきてつくづく思いますが、
個人開業、自分ひとりでの支援には、どうしたって限界があります。
クライアントさんの状態や悩みによって、
行政、医療機関、障害者支援施設、雇用支援施設、専門相談窓口などなど、
利用できるサポート資源は、意外とあります。
そしてそれらは、利用できるものなら、
積極的に活用した方がいいと思います。
餅は餅屋ですし、カウンセラーにとっても、クライアントさんにとっても、
頼れる所、そして支援の目や手は、複数ある方が心強いのではないでしょうか。
ただそれらの支援が、クライアントさんを混乱させたり、
対立したりするものでは良くないでしょう。
ですから、「連携」とか「役割分担」を意識して、
目指すところは「クライアントさんの利益」。
それが望ましい形だと思います。
以前から、一人の限界や、周りとの連携は意識しているつもりでしたが、
今回、公認心理師の勉強をしたことで、ますますその自覚が高まりました。

公認心理師になって、失ったもの
失った、という言い方は大袈裟かも知れませんが・・・
「現時点においては」、失った、デメリットだ、と感じている部分もあります。
それは、以下の3つです。
【1】手間とお金
【2】心理支援を選択する自由
【3】11年間の非常勤職
そして、これらは全て、
「主治医の指示」問題から 来ています。
同業者や関係者の方には、あ~と、
想像いただけるのではないでしょうか。
公認心理師「主治医の指示問題」
そうです。
下の法律による制約です。
◆第42条2項
公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要するものに当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
しかも厚労省の通達によると、この「指示」は、
「なるべく文書で取るように」となっています。
そして この法律に違反すると、資格取り消しという行政処分もあるのです。
ちなみに、私が関わっている全てのクライアントさんが、
精神科や心療内科に通院している訳ではありません。
ですから、通院をしていないお客様には、全く関係ない話なのですが、
一部の通院中のお客様と、その主治医の先生には、
上のような法律がある以上、協力をお願いするしかありません。
そこで私は、主治医の先生に書いていただく書式
(「主治医の心理支援意見書@i Balance」)を製作し、
なぜ、これを書いてもらわなくてはいけないのか、
その説明書も添えて、クライアントさんや関係各所に、
これをお願いしたいと説明、協力を求めてきました。
真面目にそのような形を取ってきた中で、
以下3つの不自由と、失うものがあったのです。
失ったもの【1】手間とお金
まず、「主治医の心理支援意見書」を取得するまでに、
意外と、手間やお金がかかるのです。
私がクライアントさんにお願いすることもそうですし、
クライアントさんが、通院中のお医者様にお願いする時もそうです。
無理強いはできないし、あくまでお願いできるなら…
と低姿勢にお願いしているのですが。
病院によって、書いてくれたりくれなかったり、
あるいは、無料で出してくれる所もあれば、
結構いい金額を請求されてしまうこともあります。
(上の意見書は、いわゆる「診断書」ではないし、
お医者様の書く負担を減らそうと、記入に5分も掛からないような、
簡単な形式にしたのですが…。)
この料金負担をどうするか、本当に悩んだのですが、
お客様に負担させるのはやはり申し訳なく、
結局カウンセラー側で負担することにしました。
時には5000円以上を請求されてしまうので、
正直、売上的には その分を失っているのです。
【2021年追記】
その後、公認心理師である、周囲のセラピスト仲間に確認したところ、「お客様負担」で意見書発行をお願いしている方が多いことが分かりました。現在では私も、「恐れ入りますが…」とお伝えし、お客様ご自身の負担をお願いしています。
失ったもの【2】心理支援を選択する自由
「主治医の意見書」を何とか書いてもらえたとしても。
そこにある、主治医の意見や指示は、
なんというか・・・結構「保守的」なんです。
私がメイン療法として扱っている「SE ™療法」などには、
消極的というか、警戒している印象を感じます。
ですが、カウンセラーが、
このクライアントさんにはこのアプローチを提供したい。
合っていそうと思っているのに、
それが主治医の指示で提供できないことがあるとしたら。
それって、ものすごく不自由だし、
お客様に不利益ですら、ないでしょうか。
ところで、上の法律では「指示」という強い書き方がしてあるのに、
私の方で「意見書」というやわらげる書き方に変換して文書作成をお願いしているのは、
正直意図的にやっています。
私が作った意見書では、こちらが提供できる心理支援メニューを複数並べ、
その1つ1つに、「積極的に提供してほしい…〇、
カウンセラーの判断に任せる…無印、あまり提供しないでほしい…△」
という3択から、「主治医の意見」を記入してもらう。
そのような形で、「指示というか意見」を仰いでいます。
だって、例えば 私のところに、
SE™(ソマティック・エクスペリエンシング®)療法 を受けたくて、
お金を払って来ているお客様がいる。
でも主治医に「SE™療法はNG!」そんな「指示」を出されてしまったら・・・。
やっぱり、困るじゃないですか。
だから、あくまで「主治医の意見」として伺う。
こちらも、「意見」は参考にさせていただく。
それが、精いっぱいの妥協点だと思うのです。
もちろん、クライアントさんの状態や症状によっては、
今は この心理療法をやらない方がいい、というケースはあります。
ですが、そのような時は私の方でも多分わかりますし、
ご本人にも、直接そのように伝えます。
SE™療法に限らず、今は、世界中で様々な新しい心理療法が生まれ、
その効果や実績が、論文で発表されたり、書籍も出たり、注目されたりしています。
SE™療法だって、日本での専門家養成トレーニングが始まってから、
もうすぐ10年です。
一部の精神科医も、学びに来ているくらいの療法なのです。
その辺りを、意見書を書いてくださった主治医の先生は、どこまでご存知なのかな・・・
失礼ながら、そんなことを考えてしまいます。
失ったもの【3】11年間の非常勤職
これまで書いてきたように、「主治医の意見」を文書でもらうことは、
現実的に、いろいろと厄介な面がある訳です。
この厄介なことを、厄介なんだけれど、
法律だから何とか実施させてもらえないか・・・と、
私は、11年以上産業カウンセリングを務めてきた企業に、打診してみました。
結果・・・「難しい」。
私も、法律を順守できないことは
「厳しい」。
そのため、本当に残念だったのですが、
契約期間満了とともに、私から勤務を終了させていただく結論となりました。
そう、職を1つ失ったのです。
企業側は、「今までと同じ形で働いてもらえるなら、続けてほしい」
と言ってくれたのですが・・・
私も、毎月 固定給を頂いていた仕事を失うことは、
結構な痛手だったのですが・・・
ですが、せっかく取った国家資格です。
開業カウンセラーとして働いている以上、
やっぱり、この資格を持っていることは、表に出したい。
そして、コソコソと後ろめたいことはせずに、堂々と活動をしたい。
そこは、譲ることができませんでした。

公認心理師、私の「物申したい」!
上のような現状を踏まえて、私の「物申したい」です。
そもそも公認心理師は、「国民の心の健康」に「寄与する」ことを期待され、
つくられた国家資格のはずです。
「多職種が連携」して、国民に貢献することを期待されて、
つくられたもののはずです。
それならば、その使命を果たしやすいように、
国も現状を知り、環境整備をしてほしいです。
そして、精神科医の先生たちも、
もっと協力をしてほしいし、理解をしてもらいたいです。
具体的には、例えば 以下の3点です。
1、主治医の指示(意見)を、無料に!
2、医師とカウンセラーを対等に!
3、新しい療法も知ってほしい!
そうでないと、公認心理師が「国民の心の健康」に、
「寄与」しづらいじゃないですか・・・。
まさか、寄与しづらいように、医師の尊厳と利益を守るために、
作られた法律じゃないですよね・・・?
*****
以上、普段は ネットで下手なことは言わないように、
結構「守り」に入るタイプなのですが、
同じような悩みをもつ同業者もいるんじゃないか。
私も、今の複雑な思いを書き始めると、やっぱり書きたいし、伝えたい!
そうなってしまい、ついつい、ここまで書いてしまいました。
同業者の方、関係者の方、よろしければご意見くださいませ。
【2019年9月4日追記】
ご本人に許可をいただいて、facebookで頂いたコメントも、こちらに転載しました。
貴重なご意見を 共有しましょう♪
(尚、コメントは書いていただいた後の 承認制になっています)





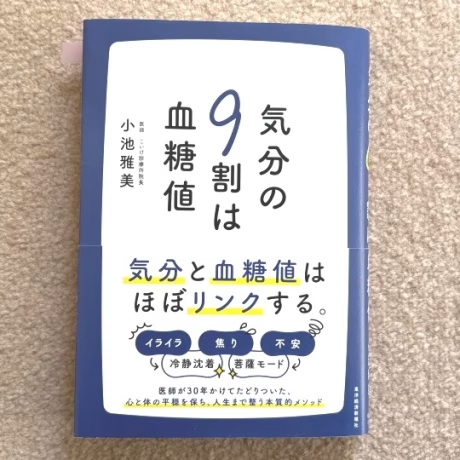

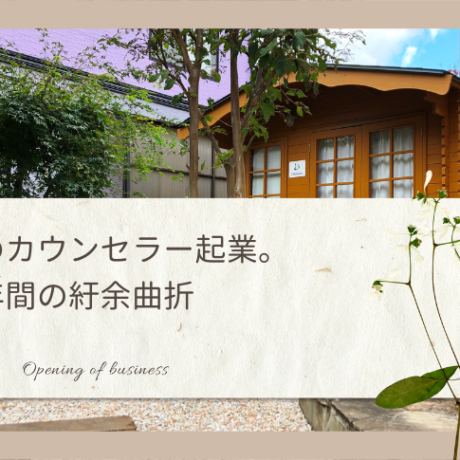
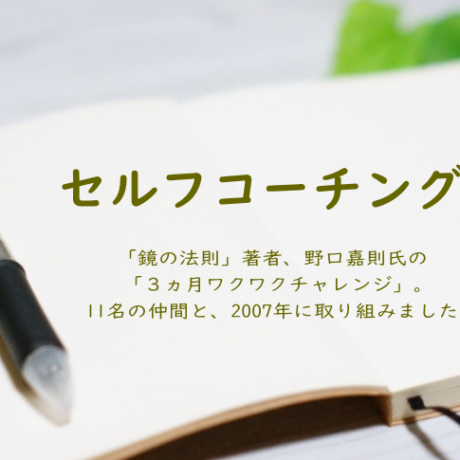
福田先生
ありがとうございます。
はい。結構ビビりではある、私です。(^^;)
でも、現場の声として、ぜひ国に届いてほしいなと思います。
支援のために難関な資格取得をされたはずなのに、そのことによって活動が制限されるとは。
相談援助職は全てと言っていいほど、医師を頂点としたピラミッドの世界の中でしか、動けないのだと、私は実感しています。
Hisayoさん
そうですね…。
的確な見解だと思います。
私が勤めていた企業の産業医さんは、カウンセラーである私のことも、「先生」と言って、尊重してくれるお医者さんだったのですが…。
全体としては、世間の認識とかいろいろな要素もあって、「お医者様はエライ。逆らえない。」になりがちだなと感じています。
読ませていただき、異業種ですが、とても勉強になりました。ありがとうございます。
私は違う業種の非常勤ですが、来年度から似たような状況になりそうです。
シェアさせてくださいm(__)m
Yさん、シェアありがとうございます。
Yさんの業種でも、似たようなリスクが起きそうなんですね。
今回のことで、私はとにかく、雇用されなくても個人事業だけで立っていける、そんな工夫や見直しをしていこうと、決意しました。
この件は、公認心理師が成立する際に一番心配され懸念されていたことですよね。実際に公認心理師がうまれたことから、またさらに議論が進んで必要な運用の改訂が更にされていくかもしれません。法律は杓子定規に捉えるだけではなく、どう解釈して運用することが実際に即した運用になっていくので、こんなふうに運用について解釈している方もいたのでご参考までに。
https://www.cocolabo.me/kounin-dr/
匿名希望さん
ご紹介の記事、こういう風に解釈、運用している人もいるんだ、と参考になりました。
私も、クライアントさんに説明して本人が望まない場合は、それで終わりにしましたが、その投げかけ自体を、もっとライトにしている印象ですね。
とても参考になりました。ありがとうございます
こちらこそ、いつ何時でも変化を受け入れるのだと気持ちを決めていきます。そもそも私は非常勤ですから、凪が続くわけがなかったのです( ̄▽ ̄;)
はじめまして。私はクライエント側の者ですが、「医師の指示」条項にかなり悩みました。精神科クリニックに通院してますが、そこには心理職はいません。なので外部機関でカウンセリングを受けようと思いました。法律ではこの場合も医師の指示が必要ですが、私はカウンセリングに医師が関与してくるのは望みません。ここで法律に違反しないようにするには、私は精神科への通院をやめなければなりません。まず通院を中止し、そのあとカウンセリング機関に行くしかありません。この条項は、カウンセリングを受ける自由を侵害するものだと思いました。
マレさん、コメントをありがとうございます!
そして、いただいたコメントに気づくのが遅れ、お返事が遅くなりました。恐れ入ります。
さて、この条項は本当にやりづらいものですよね。
ちなみに 私のカウンセリングルームでは、下記ページのような形で「医師の指示」をもらう形を2年以上やっております。
◆アイバランスの「通院中の方へ」ページ
https://i-balance.jp/to-patient/
意見書を書いてもらうのに 一定の料金を請求されることが多いので、その点は、クライアント様に申し訳ないと感じています。
ですが、最初にこの手続きさえ取ってしまえば、その後主治医が 介入や指示をしてくることは、今のところないですね。思ったよりは穏便に?自由に? カウンセリングを実施できている現実があります。
また上の内容は、カウンセラーが「公認心理師」である場合だけ該当するものなので、そうでなければ、医師の指示自体、(法的には)必要ありません。
もちろん、通院中の方が 別機関でカウンセリングを受ける時は、とりあえず口頭でもよいので、主治医に断りは入れたほうがいいと思います。
ですが、カウンセリングを受けることを否定するようなお医者様は、実際にはあまりおりませんので、通院を中止してからとか、そこまで心配しなくても、きっと大丈夫だと思いますよ。
1つの参考になれば幸いです。
貴重なコメントをありがとうございました。